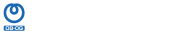電友会北海道地方本部-電電こぶし会会則
(名称)
第1条 本会は「電友会北海道地方本部電電こぶし会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の本部及び事務局を札幌市中央区北1条西4丁目2-4NTT大通4丁目ビルC棟4Fに置く。
(会員)
第3条 本.会の会員は、日本電信電話公社(逓信省、電気通信省及び琉球電信電話公社を含む)及び日本電信電話株式会社並びにそのグループ会社の退職者で入会を希望する者とする。
2 前項以外の者であっても、本会の趣旨に賛同し、理事会で承認した者は会員とすることができる。
(準会員)
3 本会の会員であった者及び会員となる資格のあった者の遺族で本会に入会を希望する者は、準会員として入会することができる。
(賛助会員)
4 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会に協力する団体とする。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定、福祉の増進を図り、あわせて日本電信電話株式会社並びにそのグループ会社(以下日本電信電話株式会社等という)の事業及び業務に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員柑互の連絡親交を密にし、会員の生活の安全と福祉の増進を図るために必要な事項。
(1)名簿の発行
(2)会報、情報誌等の発行
(3)懇親会、講演会等の開催
(4)サークル活動、レクリェーション活動等の実施
(5)慶祝及び弔慰
(6)その他必要とする事項
2 日本電信電話株式会社等の事業及び業務に寄与するため必要な事項。
(1)日本電信電話株式会社等の事業及び業務に関する周知・啓発活動
(2)地域社会への貢献活動、地域情報の提供
(3)各種行事等への積極的参加及び支援
(4)日本電信電話株式会社等からの業務の受託
(5)その他必要な事項
3 エヌ・ティ・ティ厚生年金基金、エヌ・ティ・ティ健康保険組合、(財)電気通信共済会その他の関係機関との連絡協調。
4 その他、目的を達成するために必要な事項。
(地方支部)
第6条 本会に次の地方支部を置く。
函館地方支部・旭川地方支部・釧路地方支部・北見地方支部・小樽地方支部・帯広地方支部・室蘭地方支部・ドコモ地方支部
2 地方支部の役員、規約及び業務運営については、各地方支部の定めるところによる。
3 前項の内、地方支部に関する役員、規約、年度決算、その他重要と認められる事項は地方本部に報告するものとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は次による。
(1)会長、副会長は理事の中から理事会で推薦し、評議員会の承認を得るものとする。
(2)理事及び監事は評議員会で選任する。常任琿事は琿事の中から会長が指名する。
(3)地方支部長は、その職につくと同時に本会の理事に選任されたものとする。但し、次の評議員会で承認を受けるものとする。
(4)理事及び監事の欠員補充の必要を認めるときは、会長がこれを選任することができる。ただし次の評議員会で承認を受けるものとする。
(地方支部の役員及びその選任)
第9条 第6条の2による。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 地方支部長は会長を補佐し、所属支部の業務を統括する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。また欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の任期とする。
(機関)
第12条 本会の機関は評議員会、理事会、常任理事会、拡大常任理事会とする。
(1)評議員会は第13条により選出された評議員をもって構成し、最高議決機関とする。
(2)評議員会は年1回会長が招集する。また理事会において必要と認めたときは、臨時に評議員会を開催することができる。
(3)評議員会は次の事項を決議する。
ア事業計画 イ予算及び決算 ウ役員の選任 エ会則の変更 オその他の重要事項
(4)評議員会の議長は評議員の互選による。
(5)理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、随時必要に応じて会長が招集する。
(6)理事会は会長が議長となって、会務に必要な重要事項を審議決定する。なお審議の内容が明確なものについては、書面により審議決定することができる。
(7)常任理事会は、会長、副会長、常任理事、拡大常任理事会は常任理事会メンバー及び各支部長をもって構成し、会長が議長となって会務の執行に関する事項を審議決定する。
(評議員の選任)
第13条 評議員の選任は会員100名につき1名の割合で選出し理事会で選任する。ただし地方支部については次の定数により支部長が選任する。
また本部評議会は、本部会則にもとづき理事会で選任する。
(1)所属支部会員が100名未満 1名
(2)同じく100名を超え150名まで 2名
(3)同じく150名を超え200名まで 3名
(4)同じく200名を超え250名まで 4名
(5)同じく250名を超え300名まで 5名
(6)同じく300名を超え350名まで 6名
(7)同じく350名を超え400名まで 7名
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、第11条を準用する。
(事務局)
第15条 事務局には事務局長を置き、会務を掌握する。
事務局長は常任理事の中から会長が指名する。
(定足数及び議決数)
第16条 評議員会は、現在定員の3分の2以上、理事会は現在定員の2分の1以上の出席をもって成立し、その出席者の過半数をもって決議する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(顧問、参与、相談役)
第17条 本会に顧問、参与、相談役を置くことができる。顧問、参与、相談役の範囲は次によることとし、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(1)顧問は東日本電信電話株式会社北海道事業部長とする。
(2)参与は東日本電信電話株式会社北海道事業部の上記以外の関係幹部とする。
(3)相談役は本会の会長経験者とする。
(会計)
第18条 本会の経費は会費、賛助会費、業務受託費、寄附金その他の収人をもって充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
3 会員は毎年4月中に年額3,000円の会費を納入する。新しく会員としての入会希望者は入会時に1,000円の入会金及び会費として、入会時期が4月1日から9月30日までは3,000円、10月1日から3月31日までは1,500円を納入する。次年度以降の会費は毎年4月中に納入する。
4 夫婦会員の会費は年額4,000円とする。
なお、一方が既に会員であり、新たに夫婦会員となる場合の入会金は免除のこととし、その年度の会費は1,000円とする。また、夫婦が同時に新しく入会する場合の入会金は1,000円、会費は年額4,000円とする。次年度以降の会費は夫婦で年額4,000円とし、この会費は毎年4月中に納入する。
5 準会員の会費は年額1,000円とする。この会費は毎年4月中に納入する。(入会金は免除)
6 会費未納者に対し納人督促するも、2年度以上会費を納人しない場合には、会員としての資格を喪失したものとみなし取扱うこととする。
7 賛助会員の会費は理事会において決める。
8 懇親会等における会費は、その都度必要額を出席会員が負担する。
9 本会の会計は、事務局が担当する。
10 本会の会計は、監事の監査を受けるものとする。
(その他)
第19条 本会則に定めのない事項及び事業執行の細則は理事会において定める。
附則
本会則は昭和39年7月25日より実施する。
昭和44年7月20日 一部改正
昭和46年7月24日 一部改正
昭和57年7月31日 一部改正(会長、副会長、理事、監事は総会で選出、事務局に事務局長を置く)
昭和58年7月30日 一部改正(参与制度の新設、総会の成立要件)
昭和59年1月21日 一部改止(年会費の改止)
昭和60年7月27日 一部改正(日本電信電話株式会社発足に伴う語句の修正及び第20条の一部改正)
昭和61年7月26日 一部改正(監事は理事会に出席し、監査業務に関連した意見の具申ができる)
平成3年 6月 1日 一部改正(電友会発足に伴う改正)
平成6年 5月13日 一部改正(評議員の選任の割合〔5〕~(7}を追加)
平成7年 5月12日 一部改正(会員の資格対象にNTTグループ会社の退職者を追加)
平成8年 5月11日 一部改正(相談役の委嘱について会長経験者のみとする)
平成9年 5月23日 一部改正(本部評議員の選任について、理事会で選任することを追加)
平成11年7月 1日 一部改正(NTT組織再編成に伴う組織名の修正等)
平成21年5月22日 一部改正(入会時期による会費の額、夫婦会員の会費、会員資格の喪失を追加)
平成30年5月28日 一部改正(事務所第2条 事務所移転に伴う修正)
(事業第5条 運営実態に合わない項目の削除)
(地方支部第6条 岩見沢地方支部は地方本部へ統合のため削除)
(機関第12条 拡大常任理事会を機関に追加)
(顧問、参与、相談役第17条 現行組織に合わせ修正)
(会計第18条 年会費の改正<平成31年度から改正>)
令和6年 5月28日 一部改正(会計第18条 年会費の改正<令和 7年度から改正>)
令和7年 5月30日 一部改正(地方支部第6条 苫小牧支部は令和7年6月以降、北海道地方本部に統合のため削除)
理事会決議事項
昭和40. 1.19 会員とその配偶者死亡の際弔電を贈る。
昭和49. 8. 8 80才以上の者には会費免除する。但し、在籍10年以上とする。
昭和55. 7.18 会員死亡の場合の香典を5千円とし、役員は香典と供花とする。
昭和55.11.24 支部への「交付金」を「運営補助費」に改め、年度毎補助額を次のとおりとし、支部を通じ、当該年度会費を納入した年度末の会員数(高齢者会費免除者を含む)により、翌年度の「運営補助額」を定める。
50名未満70,000円
80名未満80,000円
100名未満100,000円
150名未満150,000円
200名未満190.000円
250名未満230,000円
300名未満270,000円
350名未満310,000円
400名未満350,000円
昭和59.7.28 会費免除会員は毎年度末(3月31日)で満80才以上、且つ在籍10年以上の者を翌年度から対象とする。
昭和59.7.28 傘寿該当会員(毎年1月1口~12月末]の間に満80才となる会員)は「傘寿記念品」を贈呈する。
平成 2. 7.16 「支部運営補助費」を2倍に増額し、200名未満の分を追加する。
平成 2. 7.16 会員名簿は毎年1回発行する。
平成 3. 2.18 評議員会の定足数について3分の2以上の出席と規定(第16条)しているが、委任状の提出があった場合は出席者とみなすことができる。
平成 6. 5.20 「支部運営補助費」の300名未満から400名未満の分を追加する。
平成14. 5.24 会員死亡の場合の香典額を1万円に改定する。
平成15. 5.30 「支部運営補助費」を増額改定し、50名未満の分を追加する。
平成15. 5.30 会費免除会員は、平成17年度以降(平成16年度末に満80才となる者から)廃止する。
ただし、平成16年度以前の会費免除会員については継続して会費免除する。
平成16. 5.28 新規入会者の年会費を入会時期が4月1日から9月30日までは2,000円とし、10月1日から3月31日までは1,000円とする。ただし、人会金は会則の通り。
平成17. 5.27 電友会北海道地方本部の事業活動活性化施策として、「女性部会」を組織化し平成17年度から実施する。
平成19. 5.31 電友会北海道地方本部の「個人情報の取扱いについて」を制定。
「会員名簿」の発行周期を平成19年度から隔年発行。
平成20.5.28 10年以上の永きに亘り役員・評議員として、電友会の事業運営にご尽力いただいている方々に対して、役員等退任時に感謝状等の贈呈を決定し、平成20年度退任役員から適用。
平成20.5.28 夫婦会員の会費は年額3,000円とし、1,000円の減免措置を設ける。
なお、一方が既に.会員であり、新たに夫婦会員となる場合の入会金は免除のこととし、平成20年度から適用。
平成21. 5.22 支部への「運営補助費」配賦基準を{前年度末会員数×1,150円}とし、平成21年度から適用する。ただし、「運営補助費」の最低配賦額は80,000円とする。
平成26.1.27 従来の「常任理事会」に今後は常任理事・各支部長からなる「拡大常任理事会」を追加する。
平成27.5.25 会員勧誘を施策の一環として、ライフプラン研修に参加した社員の中で電友会活動に興味を示した者に対し、一年間、会報を無料で提供する「おためし会員」制度を導入する。
平成27.5.25 近年、パークゴルフ等のサークル活動にご夫婦で参加するケースが多く見られるようになったことから、本会則第3条第2項の規定に則り奥様又はご主人がNTTOBでない場合であっても「夫婦会員」になることができるものとする。
平成28.5.31 個人情報保護及び財政面を考慮し、2年サイクルで実施してきた紙ベースでの「名簿の発行」は取りやめ、希望者に対しては「CDロム化」したものを配布するか、電話での問い合わせについては事務局が問い合わせ先の会員に諾否の確認をとるなどして個別に対応する。 なお、本件については会報第209号、210号にて会員に周知を図る。
平成30.5.28 支部への「運営補助費」配賦基準を{前年度末会員数×1,250円}とし、平成31年度から適用する。
令和3.5.24 ドコモ支部を追加する。
令和5.5.30 昭和40年1月19日の理事会決議事項である「会員とその配偶者死亡の際弔電を贈る」は、葬儀スタイルが変化(家族葬や一日葬など小規模化・簡素化して行うことが多くなってきている)こと等を踏まえ、令和5年6月1日以降廃止する。
令和6.5.28 平成14年5月24日の理事会決議事項である「会員死亡の場合の香典額を1万円とする」は、財務状況等を勘案し、令和6年6月以降に訃報連絡が入ったものから香典額を5千円に改定する